 インダストリアルデザイン・
インダストリアルデザイン・
アーカイブズ研究プロジェクト
Industrial Design Archives Project
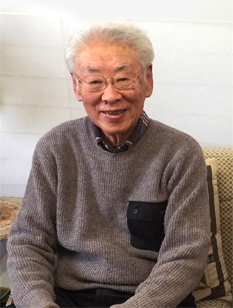
デザイナー達の証言 03
昭和のデザインを生きる
熊谷 和郎Kazuo Kumagai
1928年 大阪市生まれ。1946年 大阪市立工芸学校を卒業後、阪急室内装飾株式会社に就職。その後、近畿広告株式会社を経て、1951年 三洋電機株式会社に入社。沢田重隆、木庭光を顧問とする広告・宣伝分野でコーポレートブランドの創成に関わる。1961年 工業意匠部の設立とともに同部へ異動。部長に就任した富永直樹を支えた。1975年 工業意匠部はデザインセンターへと名称を変更。1984年 デザインセンター長に就任。1988年 三洋電機を定年退職。1998年まで、宝塚造形芸術大学ビジュアルデザイン科教授として後進の指導にあたった。
街も人も疲弊しきった戦争直後。熊谷和郎氏は、まだ市民権を得ていないデザインという言葉、デザイナーという職能とともに、ひとつずつ経験を積み重ねてきた。その歩みは、戦後昭和がどのように、そしてどのような「デザイン」という仕事をつくりあげてきたかを雄弁に語る。1951年に三洋電機に転職した若き日、広告マンとして業界初のプラスチックラジオSS-52(1952年)や国産第一号機となる噴流式洗濯機SW-53(1953年)の発売と大ヒットに立ち会った。本来は営業部の広告係。今で言えばグラフィックデザイナーというポジションにあったが、ふとしたきっかけから工業意匠部に異動することになる。そこは畑違いの製品設計、インダストリアルデザインの世界である。しかし後にデザインセンター長に就任。入社の頃とは比べものにならない数に膨れ上がったデザイナーたちをとりまとめ、サンヨーブランドを牽引する。デザイナーをめざし、デザインを学び、デザイナーとして仕事をするという、視界の開けた道がなかった時代。IDAPによる「デザイナーの証言」シリーズ第3回は、熊谷氏のキャリア初期のエピソードを聞き、デザインを取り巻く当時の環境を紹介する。
戦争と大阪市立工芸学校について
昭和17(1942)年に大工(大阪市立工芸学校・現在の大阪市立工芸高校)の工芸図案科に入学しました。親の影響があると思います。親父が自営の図案家(現在のグラフィックデザイナー)で、自宅で仕事をしていましたから、そばでずっと見ていたんです。
2年生の頃は、(勤労動員で)ほとんど工場で働かされましてね。先生も駆り出されて。学校も5年制から4年制に短縮されました。ところがね、終戦後の昭和21年に5年制に戻ったんです。ですから、この年に卒業する予定だった私は、4年で卒業してもよし、5年いてもよし、となったんです。お恥ずかしながら、実はこの時、京都高等工芸学校(現在の京都工芸繊維大学)を受験して落ちましてね。5年に進むことにしました。
京都高等工芸、というか京都工業専門学校は図案科(註1)がなくて、仕方がないから建築を受けたのですが、まぁ箸にも棒にもかからんかった。門をまたいだだけ(笑)
註1:京都高等工芸学校は、戦時中の1944年、京都工業専門学校と改称。図案科を建築科に変更している。戦後の1949年、京都工業専門学校と京都繊維専門学校が母体となり、京都工芸繊維大学が開学。1954年に工芸意匠科が設置された。
最初の就職は?
戦争で家は焼けるし、生活もあまり楽ではなかった。そんなとき新聞で阪急室内装飾の求人広告を見つけたんです。
設計課の図案係として就職しました。この会社の主な仕事は、阪急百貨店が受注した注文家具の設計・製作と東宝系の劇場の内装関連の設計・製作でした。宝塚歌劇場とか、梅田劇場やOS劇場、神戸三宮劇場とかね。戦争で梅田も三宮もほとんど全滅ですよ。だからその復興の仕事ですね。なかでも一番大きな仕事は、米軍の接収が解除された宝塚歌劇場の復活でした。仕事の半分ぐらいは宝塚でしたね。
どのような仕事を?
私が関係した仕事は、舞台周りとロビーの内装備品に入れる広告が主でした。舞台周りだったら、緞帳や脇の袖幕がありますが、それにみんな広告が入っていた。ほかに例えば、観客席の連結椅子の背もたれ後ろの広告。当時ピアス化粧品とかが多かったですね。
緞帳と言えばね、綴れ織が本格的なものなのですが、当時あまりコストをかけられなかったから「書割り緞帳」というのがあったんです。つまり織物風に「描く」。テントに使われるような分厚いキャンバス地に。日展作家の佐野(猛夫)先生が描いたシリアの模様の原画を拡大して、広い場所がないから京都のお寺のお堂にキャンバス広げてね。カゼインで溶いた岩絵具をバケツにいれて、7〜8人でタワシのようなもので塗り込むように描きました。2ヶ月ぐらいかかりましたか。ある程度でき上がったら、佐野先生がチェックするんですが、そんな大きなもの、立って見たところで全部は見えませんよね。だから、お堂から外にキャンバスを出して、先生は木に登って上から見るんです。
梅田の地下劇場とか、小さい劇場の緞帳は、デザインからやらせてもらいました。その時はアップリケで作りました。そんなこんなで1年半ぐらいお世話になりましたが、劇場復興の仕事も一段落してきたので、辞めることにしたのです。その後、近畿広告(後の大広)という広告扱いの会社(広告代理店)に入りました。
三洋電機に入社したのは?
大広時代、工芸学校の恩師から電話があって。「遊びにこないか」と。この恩師から三洋を紹介されました。三洋電機は製作所から株式会社に改組して成長途中にあって、本社も手狭な状態でした。会社を訪問し常務にお目にかかったら、今は座る席もないけど、近々新築中の本社屋ができるから、できたら来てくれとね(笑)昭和26(1951)年の5月ですか。三洋電機に入社しました。配属は営業部のなかの広告係。当時は本社に、社員100人もいなかったんじゃないかな。
プラスチックラジオSS-52発売の前年の入社ですね
(プラスチックラジオSS-52宣伝カーの写真を見ながら)当時はね、これは誰の担当、あれは誰の担当というものはありませんでした。この宣伝カーには上司の川本さんと庭窪工場の工場長をされていた川本さんのお兄さんが製作に関わっているんですが、私も一緒に現場に行きました。トヨタの最新モデルのトラックのシャーシに、SS-52型ラジオの外観をそっくり拡大したボディーを、大阪市港区のある板金工場で作りました。当時としては珍しい宣伝カーで、日本全国の街々をコマーシャル放送を流しながら走り回ったので、話題を呼んだものです。当時、三洋の商品はまず、発電ランプ、自転車の錠前やブザーがあって、他にトースターとミキサー。そしてラジオのパーツ(スピーカーやバリコン、中間周波トランスなど)があって、つまりね、ラジオを作るための下地はあったんです。

国内初のプラスチックラジオ《SS-52》(1952年)

トラックの荷台にプラスチックラジオの
巨大な模型を取り付けたラジオ型の宣伝カー

国内初のプラスチックラジオ《SS-52》(1952年)
インダストリアルデザインについての意識は?
私が言うのもなんだけど、大阪の工芸学校などではレベルの高い教育が行われていました。だからデザインを専門とする世界では、バウハウスなどに学んだりと、デザインの公共的役割への意識はあったんです。
意識はあったけど、職能が明確ではなかった。
ブランディングについては?
初代の宣伝部長(亀山太一)は、経営理念と広告の関係、広告のあり方には非常に神経を尖らせていました。亀山部長を中心にブレーンの沢田さん、木庭さんたちと、毎月広告の企画会議を開いていたんですけど、ここでブランドのあり方も討議しました。松下電器だったら、社名は松下電器、ブランドはナショナル、社章は松葉ですが、三洋も同様でどうあるべきかと。社名、ブランド、社章を含めたCIのさきがけ的なことを議論しました。「世界に誇りうる精度の高い仕事」と社是も決めてね。正月の一頁広告を作るときのことです。商品広告が主流のなか、企業広告が出始めていた頃です。昭和30年代の中頃かな。

新型冷蔵庫の新聞広告
(イラスト:沢田重隆|1961年)
工業意匠部について
社長(井植歳男)と富永先生がめぐり会うことになったのは、ラジオキャビネットのプラスチック成形を積水化学工業に依頼したことがきっかけではないでしょうか。社長は「この人は三洋に必要」だと直感したのだと思います。三洋に来てくださるよう先生を説得されました。社内報には社長と富永先生のデザイン対談も載っています。
工業意匠部ができる前から、製品デザインに関わっている社員がインダストリアルデザインについて意見を交わしています。同じように社内報に掲載されています。彼らの問題意識も高かったです。
その後、ようやく本社に工業意匠部ができて、いわばデザインセンター的な役割を担おうとしたけれど、実際はなかなか難しい。この頃は工場に配属されたデザイナーは、必ずしも意匠係とか職名がついているわけでもなくて。ばらばらだったんです。工業意匠部の組織的な位置づけは本社スタッフになるわけですが、このことについて、後に三洋から京芸(現在の京都市立芸術大学)に移籍する高井(一郎)さんと富永先生と私たちで、いろいろ議論しました。要は、「インダストリアルデザイナーはスタッフかラインか?」。つまりデザイナーは本社か工場かどこにいるべきかという議論です。結論から言えば ―― 結論なんか出ない。あえて言えば、頭はスタッフで手(身体)はライン。
工場でずっと仕事をしていると、そこから離れることは仕事の基盤が崩れるということです。身体は工場に置くべき、と思うところですが、でも工場にいるとどうしても「作り勝手」優先になってしまいます。本社スタッフが、「作り勝手本位のデザインするな」、商品として使う人のためにデザインしろと言うわけですね。ところが、言えば言うほど抵抗があったりするもの。ここで富永先生の存在は大きかった。現場で抵抗があっても、先生がダメといったらダメ。ただ、現場が納得していたかは ―― 難しいですね。
私は宣伝にいた頃、富永先生を北条(兵庫県加西市にあった三洋電機工場)に案内したことがあるんです。なんで私のような入社2年目のペーペーが付き添いに指名されたのかね。でも誰かデザインがわかって、そばについている人が必要だったんでしょうか。それがきっかけなのかどうかわかりませんが、私は設立とともに工業意匠部へ異動することになりました。同じデザインと言っても平面から立体ですからね。素人です。まぁ、でも、今でこそビジュアルとインダストリアルに分かれていますが、当時は図案科から工業デザインの道に進んだ人もたくさんいますしね。
註2:《4号A卓上電話機》のデザインで知られる彫刻家富永直樹は、沖電気や積水化学でインダストリアルデザインに携わり、1955年に三洋電機の顧問に就任。1961年、工業意匠部が設置されると部長職に就き、その後取締役を務めている。

三洋冷蔵庫第一号機《SR-350》(1957年)

《19-CT1000》広告 (1967年)
三洋のデザインについて
三洋は新しい会社だったんです。当時、業界団体の電子機械工業会のなかにデザイン委員会ができて、提唱したのは東芝さんだったと思います。東芝さんが中心に動いていました。東京は御三家の東芝、日立、三菱電機をはじめとして、ほかにもソニーさんとかいろいろあった。関西は松下、シャープ、三洋と、家電メーカーは3つしかなくて、三洋が一番新しい。デザイン活動が斬新だったのは三洋だったと思います。古くなかったから、古いところがなかった。デザイナーの思うことをやらせてもらえる会社だった。例えば実験的に、5年後のかたちだけではなく機能も想定したデザインをするんです。その頃にはこんな技術が実現しているだろうと。そういうところが三洋にはありました。シリーズ商品ができる土壌も、そんなところにあったと思うのです。
単身生活者を対象とした≪it’sシリーズ≫など、さまざまなシリーズ商品を発売されました。1965(昭和40)年からのアートドア・シリーズ冷蔵庫についてお聞かせください。
《アートドア》ですが、冷蔵庫の製造方法から見てみると、本体はともかく、ドアの構造は、従来の箱形のプレス加工から、周りをくるっと巻く方法に変わりました。外側のパネルと冷蔵庫内側の成型パネル、その間に発泡ウレタンの断熱材を挟んで周りをアルミサッシで囲む構造ですから、木目調のドアが登場したわけです。木目ができるんだったら、ほかにもいろいろな模様がつけられる。つまりこの方法がアートドアに必要な条件だったのです。
昭和40年代には、花柄の商品も出てきますよね。タイガーさんの魔法瓶が最初で、三洋はまずトースター(SK-300)と電気ポット(U-300)を出しました。

アートドア冷蔵庫のラインアップ (1965年 – )
聞き手・インタビュー編集:大阪新美術館建設準備室 植木 啓子
*プロフィール、注釈文、インタビュー記事カッコ内補足においては敬称略
特集「デザイナーたちの証言」は、IDAPが現在進めているオーラルヒストリー聴取の成果から、テーマを絞りダイジェストでご紹介するものです。IDAPオーラルヒストリーは今後、報告書の発行等によって詳細を公開していく予定です。

