 インダストリアルデザイン・
インダストリアルデザイン・
アーカイブズ研究プロジェクト
Industrial Design Archives Project

デザイナー達の証言 01
脇役を極める
―三角タップという項―
可知 江苑Koen Kachi
1934年 岐阜県生まれ。59年 金沢美術工芸大学卒業後、松下電工株式会社に入社。当時の急速な家庭電化とその安全性を支えることが求められた配線器具を中心に、製品デザインや商品開発に取り組む。62年 トリプルタップ、三角タップの開発に携わり、64年の松下電工初のGマーク選定に貢献する。82年 同社総合デザインセンター所長に就任。その後、東京企画開発部長、デザイン部長を歴任し、次世代デザイナーの育成、社内のデザイン組織の改革にも力を注いだ。94年 定年により退職。助(たすく)デザイン企画を設立。自身が授かったこれまでの多くの「助」を糧に、々の生活を「助ける」デザインをライフワークとしている。
1962年に松下電工が発売を開始した小さな2つの製品がある。それは入社わずか4年目の若きデザイナーの手によるものだった。製品は2010年を前に累計生産1億個を超え、半世紀を経た現在も、ほぼ当時のデザインのまま販売されている。日本津々浦々の家庭やオフィスで「壁の花」のようにひっそりと、しかししっかりと役目を果たすその商品は、トリプルタップそして三角タップと言う。そのかたちを知っていても、名を知る人は驚くほど少ないのではないだろうか。
私たちの生活に見事なまでにとけこみ、その存在が「当たり前」になるという、デザインにとって実はもっとも難しい「頂」に達したこの2つのマルチタップ。IDAPによる「デザイナーの証言」シリーズの第1回は、このロングセラーデザインを生みだした工業デザイナー、可知江苑氏に話を聞く。
 ハイトリプルタップWH2013
ハイトリプルタップWH2013
 ハイ三角タップWH2012
ハイ三角タップWH2012
まずは松下電工に就職した動機と経緯について
僕は金沢美術工芸大学を卒業して松下電工に就職したのですが、その前に静岡大学に当時あった短期大学の工学部でエンジニアになるつもりで学んでいました。車が大好きでね。ホンダに行きたかった。そんなとき、日本でも工業デザインのコンペが開催されて、柳宗理さんが一等賞を取られて。さらに、アメリカ帰りの教授が大学に来て、「可知くん、将来はね、デザインという新しい仕事が生まれるよ」っておっしゃった。とても刺激を受けてね、それで変わっちゃった。戦争で命拾いした兄が、すぐ調子に乗る末っ子の僕に「一回やりたいことをやっておけ」と後押ししてくれてね。柳宗理さんが教えている金沢美術工芸大学に行かせもらいました。昭和33年(1958)頃から、松下電工は人材確保のために実習を始めたのです。4回生の学生を集めて夏休み中に実習をさせて、その結果に基づいて次の春に採用という制度でした。僕はデザイナーとしては初めての実習生のひとりでした。大学からの紹介でしたが、夏休みに大阪に行けるのであればと。採用にあたっては、僕は補欠みたいなものでしたが(笑)
入社後はすぐにデザイナーとして仕事を?
昭和34年の入社後、津の工場に行くことになりました。もう早速、設計部でデザインです。津の工場は、松下創業の商品であるソケットなどを製造しているところで、ユリア樹脂の成型が主体でした。ところが同年秋、事業部制が導入されたため、僕は配線器具事業部所属となって、本社(大阪府門真市)に異動しました。
当時、会社内でのデザイナーの仕事とは?
デザイナーの職務は新商品の開発です。単なる機器の設計ではなく、その時代の流れのなかで、時代の感覚を取り込むことが求められました。配線器具事業で言えば、総合企画のグループにデザインチームが入っていて、商品の企画をするメンバーが身近にいたのです。「こんなのはどうや」とか話が盛りあがると僕がスケッチ描いて、いろいろと提案しました。ほかにも配線器具の市場開発のためには何をしたらいいかとかね。話し合いをするのには実に楽な環境だったんです。
配線器具というのは、きわめてシンプル。電気といっても、蛍光灯のようなものを開発するわけではなく、身近な人、子どもでもおじいちゃんでもおばあちゃんでも誰でもが操作できるスイッチをつくることが仕事。「使いやすくわかりやすい」がいつも条件として僕の頭のなかにありました。
デザイナーの仕事の範囲とは?
製品の外形だけではなく、内側の技術的な部分にも関与しましたか?
工業デザイナーはそこまでやらなくてはならないと、僕は思っています。単なるカバーのデザインや飾りのデザインをやっているわけではない。発想があって、それを実現するための構造を考えながら、外形をデザインする。
(三角タップをドライバーで開けて)この三角タップですが、中の金属部品は2つです。でもこの2つは別のものではなく同じもの。左右ひっくり返して使っています。そしてこの黒いベースですが、これはもうひとつの商品、トリプルタップのベースと同じです。2つの商品に共通する部品です。金型を共有することによって生産性を上げてコストを下げていく。そういったことも考えるのです。

 三角タップ部品
三角タップ部品
三角タップとトリプルタップについてさらに詳しく
入社して間もなくこの2つのタップをデザインしたのですが、その頃、つまり昭和30年代、家電製品がどんどん増えていきました。だから、安定した品質で生産性の高い配線器具が必要だと考えました。生産性が低いと値段が高くなりますからね。またその当時、ユリア樹脂はカーボンを入れて作っていたので色は黒だったのです。でも、黒い配線器具って目立つでしょ。白であればどこに使っても、どんな壁でもあまり違和感が生じない、しかも完全に存在感がなくなってしまうわけではない。ところが、このアイデアがまぁ、「白いのなんてとんでもない」って、ずいぶん揉めました。なぜかと言うと、白は品質管理が本当に大変なのです。黒なら問題にならない程度の塵でも、白に入ったらもう不良品。だけど「なんとしてもやってやる」と頑張りました。結果として「こんなことできない」と言っていたことが「できた」わけですから、品質管理の現場の自信にもつながったと思います。
製造や品質管理の現場との関係はどうでしたか?
「可知はまたこんな変ちくりんなもの持ってきて」と思われていたのかな(笑)
白いタップの後に、フルカラー配線器具(スイッチ・コンセントなどの配線器具シリーズ)を手がけていますが、「前は真っ白けで、今後は《フルカラー》とはなんやっ」とか。「いろんな色持ってきて、あれやってくれ、これやってくれと、どないすんやっ」とかね。
何がよかったかと言えば、寮生活です。事業所や部署関係なく、最初の3年ぐらい先輩後輩一緒に生活するのですが、仕事の後、みんな食堂で顔を合わせます。ぐずぐず悩んでいれば、ちょっと一杯やろうかってことになる。顔の見える人間のつながりが、許容度を高めますね。それがフルカラーのような製品につながっていく。
 フルカラーシリーズ
フルカラーシリーズ
多少の無理は聞いてくれるということですね
逆に先輩から怒られることもありました。いずれにしても、セクションの壁を破る良い制度だったと思いますよ。私のような田舎者にとっては、安定した食住環境に護られているというのも大きいし。
家族的な雰囲気があったのですね。
下から上へ提案して実現というパターンはよくあったこと?
ほとんどがそうじゃないですか。こうした社風にもっとも貢献したのは社長自身(丹羽正治氏)でした。
昭和57年(1982)に、僕は総合デザインセンターの設立を提案しています。それまでは、各事業部がその事業計画に従ってそれぞれデザインを行っていましたが、イメージの統一であるとか、全体をかたちづくるデザインポリシーという部分が弱かった。個性を生かすことはもちろん大切ですが、会社が大きくなっているわけですから、対外的なイメージ、総合的なイメージの必要性を感じたのです。そこで「おい、ちょっとみんな」って感じで集まり、西三荘(京阪電車・西三荘駅周辺)で一杯やりながら、いろいろな話をして、じゃぁ上に持っていこうと。社長さんに提案を持っていったら、「よっしゃ、それで行こうか」となり、デザインセンターが実現しました。
社員の自由度が高かったということでしょうか?
社長は経営者として、人使い上手だったのでしょうね。それぞれの個性を生かし、組織運営に活かす。
トリプルタップ、三角タップともに、発売以来、基本デザインの変更なく生産され続けている、いわば不朽のデザイン。デザインした当初、デザインとしてのロングライフ、「耐久性」について意識していましたか?
当時はそこまで意識はしていませんでした。ただ、あまりうるさく変更しないでよいものを、とは考えていました。石膏でいくつも試作しましたが、設計者も生産技術のメンバーもこのかたちでと言ってくれましたね。
このシンプルなかたちのなかに、実はもっとさまざまなデザイン上の工夫、使用者に対する配慮がなされていると思うのですが
「握り」については特に配慮しました。ベースとカバーに段差があることによって、コンセントから抜くとき、握りやすく抜きやすい。ひっかかりは意識してつくりました。
可知氏にはパナソニック エコソリューションズ社(旧松下電工)で、延べ6時間近くのインタビューに応えていただいた。デザインや広報に携わる現役社員の方々を交えてのこの6時間は、インタビューというより、商品を囲みデザインについて語り合う、笑いと熱気にあふれたディスカッションとなった。松下電工の寮ではこのような議論が幾夜となく繰り広げられていたのだろうか ……
「おっちょこちょいですから、ついつい、いろんなことに手を出すんですよ」と、いたずらっ子のような笑顔を見せる可知氏に、あらためて感謝したい。
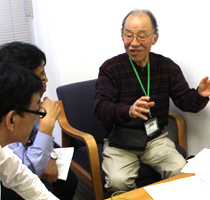
聞き手・インタビュー編集:大阪新美術館建設準備室 植木 啓子
特集「デザイナーたちの証言」は、IDAPが現在進めているオーラルヒストリー聴取の成果から、テーマを絞りダイジェストでご紹介するものです。IDAPオーラルヒストリーは今後、報告書の発行等によって詳細を公開していく予定です。

