 インダストリアルデザイン・
インダストリアルデザイン・
アーカイブズ研究プロジェクト
Industrial Design Archives Project
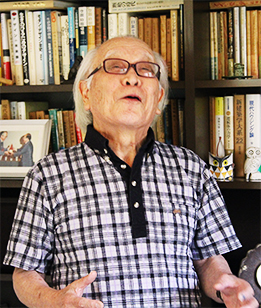
デザイナー達の証言 02
「コト」づくりのプロフェッショナル
―関係をデザインする―
巽 正和Masakazu Tatsumi
1936年 京都市生まれ。61年 京都工芸繊維大学意匠工芸科卒業後、理研光学工業(現・リコー)に入社。
64年 松下電器産業へ移り真野善一率いる本社意匠部で、各種製品単体のデザインに留まらず、生活空間の改善や新提案となるユニット、システムのデザインに積極的に取り組んだ。78年より電化本部デザイン部デザイン室長、87年には電化本部デザイン部長に就任。電化本部では、全自動ホームランドリー「ランドリーム」やひとり暮らしの女性にターゲットを絞った「BEGIN」シリーズの開発を手がけた。退職後、93年から2001年まで(財)国際デザイン交流協会の常務理事・事務局長を務め、大阪での国際デザイン・フェスティバル開催を推進した。社内、社外ともに受賞を重ね、デザインや商品開発に関する論文も多い。
「電化」がもたらした戦後日本の生活の変化。その大きさは計り知れない。そして電気の力を「便利さ」や「快適さ」に変換して私たちに届けくれるのが家電製品だ。いまや汚れた布を洗濯板にこすりつけたり、飯炊きの火の調整に気を配ったりする必要はない。洗濯も炊飯も家電製品が自動でやってくれる。
松下電器産業で数々のヒットシリーズを生みだした巽正和氏は「自動化の歴史は人間のエゴの歴史である」と言う。30年間、家電製品開発の現場で人間のエゴに寄り添いながら、70年代以降は省エネルギーやエコロジーの観点からデザイン倫理の問題にも向き合ってきた。「デザイナーの証言」シリーズの第2回は、家電商品開発をつうじて、ヒトとモノとその関係からシステム、空間、環境へと考えをめぐらせ、モノではなく、さまざまなコトの連続である生活をデザインの対象としてとらえた巽氏に話を聞く。
工業デザインの道に進むことになったのは?
小学校、中学校のころは小説家や漫画家を夢見ていました。高校に入って建築家を志すようになるのですが、新聞部の活動ばっかりやっていまして、高校時代を少しエンジョイし過ぎました。それで京大の建築に入れてもらえなくて。でも、建築なら京大だけじゃなく工繊(京都工芸繊維大学)にもあるじゃないかと次の年に調べたら、建築科だけではなく意匠工芸科という学科もあった。「意匠ならデザインかな…」程度の考えで、実際何をするのかはわかっていませんでしたが、「意匠」という言葉に惹かれましてね。意匠工芸科を受験しました。
工繊は新聞部がなかったので、演劇部に意匠工芸科の同級生5人とドッと参加しました。建築や意匠の学生が演劇で力を発揮するのは、演技じゃなくて、舞台装置や大道具小道具、衣装なのですけど、作業していると一日すぐに終わっちゃう。そんなことばっかりしているから、また勉強のほうがおろそかになりまして(笑)。
当時の就活は、4回生の夏休みに企業実習に行き、実習後の面接で内定をもらうというものでした。3回生までの成績順に実習先を決めていくのですが、まんなかぐらいの私に順番が回ってきたときに、面白そうだなぁと思えるところはカメラやリコピーを作っていたリコー(当時は理研工学)だけでした。それが縁でリコーに就職が決まったのです。
リコーから松下に転職したのは?
リコーは東京なのです。東京はいいところだけど、一生東京で生活するのは無理だと思いました。もうひとつ、リコー時代にコンペなどに参加して、自分には電化製品のデザインが合っていると感じたことが理由です。
松下電器産業ではまず本社の意匠部に配属されたとのこと
本社の意匠部では、そもそもデザイナーがいないとか、デザイナーはいるけど応援が必要とか、そんな事業部からの依頼を受けていました。私の最初の仕事は自転車事業部からのもので、自転車の荷台とかパーツのデザインでした。その後12年ぐらい本社で働くことになりますが、開発担当として、いろいろな事業部と思う存分仕事させてもらいましたね。私は開発で大切なのは、「素人の感覚をもつこと」と「素人と玄人の戦いから生まれる緊張感」だと考えています。具体的に言いますと、例えば、商品開発の応援で本社意匠部の私が掃除機事業部に行く。掃除機事業部には掃除機事業部のデザイナーがいる。彼らは掃除機のデザインについては玄人なわけです。「本社の連中に何がわかるかっ」と多分思っている。そんな玄人と、素人である本社意匠部のデザイナーは同じところで勝負してはならない。必要なのは「何でや?何でこうなってん?何でここに車輪ついてる?何でや、何でや?」ってね、突っ込んでいくこと。そうすると玄人が「何でか知らん。前の図面からこんなやった」と、実は自分自身も答えを持っていないことに気づくのです。商品化する前に、こうした議論をしっかりやっておかないといけません。
あちこちの事業部と仕事をして、全社の大きな力、オール松下の力を知りました。事業部は事業部でそれぞれハッピーであっても、力を合わせることが足りてなかった。でも力を合わせればごっついことができるんです。
力を合わせることの大切さ。具体的な事例はありますか?
まず教育機器のプロジェクト(1974-77年)がそうです。特機営業本部からの依頼でした。教育機器の分野でソニーに負けていると。商品はカタログがあるぐらい松下通信でいっぱい作っているのに、何かいい方法はないかと問われて、デザイン統合を考えました。売り込み先は学校です。具体的には視聴覚教室とか放送室とかLL教室とか。ですから、ユニット化、システム化して空間全体をデザインしたのです。商売しやすいようにと、営業がトランクに入れて学校に持っていける模型を作ったりもしました。
ほかにも、インターリビングショウの「カプセル住宅」出展(1971年)やライオンズマンション用のユニット開発(1971-73年)など、複数の事業部や松下グループ内企業との協働でユニットやシステムのプロジェクトを重ね、時には営業本部の集まりで説明しろと言われて出ていき、本社に在籍中、ずっと顔をつないできました。元演劇部の大阪弁で、目立ちたがりですからね(笑)でも、私は社内の仕事は7割から8割のエネルギーで取り組むことにしていました。あとの2割は外の仕事。JIDA(日本インダストリアルデザイナー協会)の活動、京芸(京都市立芸術大学)の非常勤講師と、できることはなんでもやっときました。
 <カプセル住宅>の一室
<カプセル住宅>の一室
そうした姿勢が全社的なプロジェクトにつながっていくのでしょうか
オール松下(電器)で取り組んだ「ニューファミリープロジェクト」(1975—77年)。これはね、えらいことだったんです。総合企画室から意匠センター(旧・意匠部)に話がありました。当時の総合企画室長が、数字のことばっかりではなくて、やっぱり世の中「あっ」と言わせる何かをやろうじゃないかという気持ちがあって始まったのです。総合企画室、意匠センターに加え、営業本部と宣伝事業部で合同委員会をつくって、事業部を製品分野別の3つのグループに構成し、そこからメンバーを出して実動部隊のワーキンググループを結成し、副社長をトップに意匠センター長の真野さんと総合企画室長を推進責任者として、ニューファミリーというコンセプトで全社的な開発提案に取り組むものでした。こうした組織づくりを含めて私がこのプロジェクトを担当し事務局を務めました。この仕事ができたのは、本社で10年間かけてネットワークをつくってきた、信頼を得てきた、その結果です。プロデューサーの役割と言うのでしょうか。組織や責任者の思いや立場を理解できるようになったと言うのでしょうか。また、本社の意匠センターが事業部のデザイン部門に対して号令をかけるだけの力をつけてきていたことも大きいです。
昭和51年(1976年)には戦後世代が日本の全人口の半分を超え、従来の日本のそれとは異なる行動様式や価値観を持って、新しいライフスタイルを形成しているわけです。それは市場開拓の上で大きな課題であって、全社的に商品開発やデザイン、販売促進を考えていかなければならなかったのです。各事業部から提案があって、それを委員会で検討し、発表展示会に出すものを決めていきました。
巽さんは事務局の役割を担っていらっしゃいますね
事業部はプロジェクトにかかわらず、元々やってみたかったことを提案してくるのです。事務局はその提案に対して、トップの理解を得るためには、営業はどう言うか、どんな技術的な強みがあるのかなど、そうしたことについてアドバイスする。提案をわかりやすくするのです。そこでニューファミリーのコンセプトと一致するなら後押しできる。内部をどう説得するのかが大切なのです。デザインはある意味無責任。いちいち責任とっていたら提案なんてできない。そう、ある意味、提案がデザインの仕事なんです。提案しなければ誰にもわからない。
この「デザイナーたちの証言」では、巽氏のキャリアの前半を集中的に取り上げている。彼はその後、電化本部に異動し、仲間たちと生活研究(消費者の意識、価値観、実感、ニーズ、ライフスタイルの総合的調査・分析)からのものづくり環境を構築し、「ランドリーム」や「キャニスター」などのヒット商品を市場に送りこむことになるのだが、その活躍に必要な力をどのようにつけていったのかを探りたいと思った。それは、感覚の鋭さや技術の確かさ以上にデザイナーに求められるものとは何かと考えることになった。巽氏は「説得する」ことを強調する。だからこそ巽語録のトップはいつも「一に忍耐、二に根性、三、四がなくて五にセンス」なのだ。
 ナショナルホームランドリー<ランドリーム>
ナショナルホームランドリー<ランドリーム>
聞き手・インタビュー編集:大阪新美術館建設準備室 植木 啓子
特集「デザイナーたちの証言」は、IDAPが現在進めているオーラルヒストリー聴取の成果から、テーマを絞りダイジェストでご紹介するものです。IDAPオーラルヒストリーは今後、報告書の発行等によって詳細を公開していく予定です。

